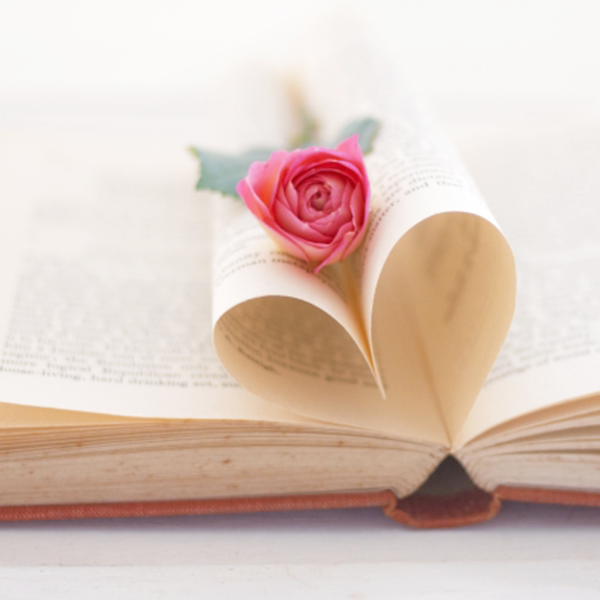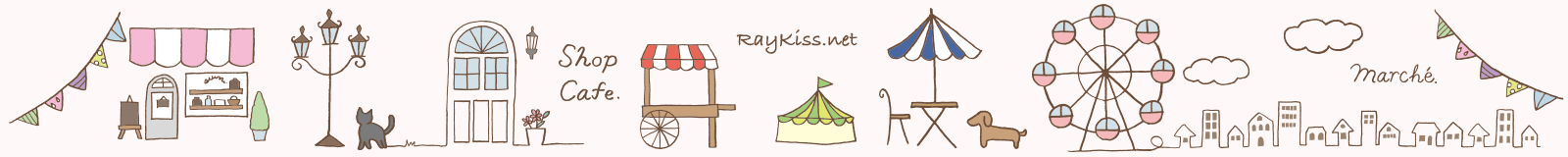
HOME > ギフト・贈り物コラム > 出産祝いのマナー・贈り物とお祝いのタイミング
出産祝いのマナー・贈り物とお祝いのタイミング
更新日:
出産祝いを病院に持って行っても良い?
出来るだけ退院後にしましょう。
産婦は授乳指導で忙しかったり、体調に変化があったり、家族との時間を大切にして過ごされています。家族でない場合は出産後に病院に行くことを避け、退院直前に産婦の様子を確認し、病院の面会時間を守って訪ねましょう。
退院後にお伺いするときはしばらく時間が経ってからにします。退院直後は赤ちゃんとの自宅での生活が落ち着いていないため、お宅にお伺いして迷惑になることがあります。
お伺いする時は、出来れば子供連れで行かないようにして、赤ちゃんを勝手に抱かないようにします。また、授乳などを行う産婦への配慮から、男性は遠慮することもマナーです。
お祝いの気持ちを今すぐ伝えたい時は、手紙、祝電、カードで気持ちを伝えるとスマートです。
出産祝いを贈るタイミングは?
出産後1~2週間、遅くても1ヶ月以内に贈ります。
赤ちゃんが生まれてから1~2週間で出産祝いを贈りましょう。遅くても1ヶ月以内に贈る理由は、受け取る側が生後1ヶ月くらいの時期(お宮参りの頃)に、お返し(内祝い)をするしきたりがあるからです。
出産を遅れて知ったり、どうしても間に合わなかった時でも心配する必要はありません。
その時は、お祝いの言葉と共に、遅くなったお詫びを書いた手紙などを品物に添えて贈りましょう。
半年以上遅れた時は、満一歳の誕生日に贈っても構いません。
出産祝いはいくらくらいのどんな物が良い?
5,000から1万円くらいの品物が選ばれています。
 5,000~1万円くらいのものに、紅白蝶結び、のし付きで贈ります。
5,000~1万円くらいのものに、紅白蝶結び、のし付きで贈ります。
表書きは、御出産御祝、御安産御祝などと書きます。
赤ちゃんは成長が早いため、衣類を贈る場合は大きめのもの贈りましょう。
産着はすでにたくさんお持ちですので、2歳くらいのサイズが喜ばれます。
おしゃれなお出かけ着より、普段着やパジャマの方が使う機会が多いのでおすすめです。
おもちゃ、絵本も定番ですがバラエティに富んでいるので、人と同じものになりにくいです。
親しい間柄であれば欲しいものを選んでもらっても構いません。
品物を選べない場合は、「ミルク代に」などと一言添えると、赤ちゃんへのお祝いの贈り物と分かるので、気持ちが伝わります。